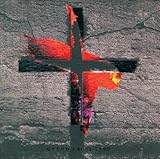2000年代最初の10年も終わりに差しかかろうとしてる頃にこんにちは。唐突ですがよく雑誌とかで見かける90年代ベストというのを俺もやってみたいと思います。
90年代と言えば Nirvana がグランジ/オルタナティブをメインストリームに叩き込んだのと引き換えに命を落とし、 Oasis と Blur がやいのやいの言いながらブリットポップのお祭り騒ぎを繰り広げ、その脇から Radiohead が独走して結局一人勝ちし、あと My Bloody Valentine が夢のような作品一枚を残して伝説と化したり Massive Attack や Portishead などのトリップホップ勢がまた別のダウナーな悪夢を描いたり、他にも Beck とか Bjork とか NIN とか様々な才能が傑作を生み落としましたが知らねー。つーか俺洋楽なんて今でこそ好きなのは色々あるけど90年代にリアルタイムで聴いたものなんて一つもねえし、Mステとか CDTV とかの音楽バラエティを最大のアンテナとして活用する邦楽大好きっ子でしたがな。そんなオイラも自分で音楽を探して聴くという行為を意識的に始めてかれこれ十数年。未だに音楽を聴き始めた90年代への憧憬/ノスタルジーを捨てきれないまま90年代の名盤を独断と偏見まみれで選んでみました。以下20枚。
20. X 「Jealousy」
日本が世界に誇るネタバンド X 。2008年に復活しても相変わらずの
大道芸人っぷりを見せつけてくれてるのは周知の通り。何故 「Jealousy」 なのかと言うと単純に 「
Vanishing Vision」 も 「
BLUE BLOOD」 も80年代リリースだからです (さすがに 「
DAHLIA」 はない) 。しかし今作は
YOSHIKI 以外のメンバーによる楽曲が比較的多く、王道ナンバー 「Silent Jealousy」 や 「Say Anything」 がメインの位置に据えられてる一方で、
TAIJI による痛快
メリケンロックンロール 「Desparate Angel」 や HIDE 作の実験的コラージュ曲 「Love Replica」 、また PATA のアコギ独奏によるシンプルな小品 「White Wind from Mr. Martin」 も全体の流れをスムーズにする潤滑油として機能し、 X の中でもヴァラエティの豊かさと纏まりの良さを両立した、最も取っつきやすい内容になってます。楽曲単位だと
「紅」 や 「Rusty Nail」 など他にも名曲が沢山ありますけど、アルバム単位のトータリティで見ればこれが一番じゃないかと。
19. cali≠gari 「第5実験室」

先日6年ぶりの復活を果たしたカリガリですが、それは既存の様式的ダークヴィジュをこき下ろしオサレ系ブームの引き金となった第7期メンバーによるもの。それ以前の彼らは 「奇形メルヘン音楽隊」 と自称するだけあってそれはそれはアレなものでして、猟奇的/タブー的テーマばかりを不協和音全開のシュールなテイストでお届けするサイコさんバンドだったのです。ギター青氏の作る楽曲はもちろん、ヴォーカル秀児氏 (≠秀仁) の強烈な電波系キャラクターも大きなウェイトを占めていた。それでこの作品は第6期最後のアルバム。昭和歌謡/ファンク/ジャズ/ビートロックなど節操のない雑食主義はこの頃から健在、なおかつ 「せんちめんたる」 では異常性愛、 「37464。」 では衝動的殺意、 「弱虫毛虫」 では少年犯罪を歌うといった風にさすがのエログロナンセンスっぷりを発揮してますが、以前よりもメロディのポップさが増加して聴きやすい作風に。最初はジャケットや曲名が薄ら怖くて聴けなかった (笑) 。でも一旦ハマるとすっかり抜け出せなくなりました。それこそ今日に至るまで。
18. 幻覚アレルギー 「JAPANESE TRASH」
元
かまいたちのメンバーによって結成された2人組ユニット。中身は金属質ギターや直線的ビートで迫るアグレッシブな演奏、 THE STALIN にも匹敵する辛辣で
アヴァンギャルドな歌詞、さらに hide に通じるコミカル & シニカルなセンス (あと人をおちょくったようなフェミニン声) がドログチャの音質の中で混じり合う粘着系アングラパンク/ハードコアであります。コレの前作 「
PSYCHE:DELIC」 が本当に
サイケデリックな致死量以上の毒濃度で、良くも悪くも聴き通すのに凄く体力の要る作品だったのですが、今作はパンク由来のストレートな攻撃性を重視し、キャッチーなフックも兼ね備えた比較的聴きやすくノリやすい内容。そのストレートさ故に本来の毒が即効性の高いものへとブーストされ、よりスムーズに脳細胞を侵していく。 「変態テロリスト」 だの 「植物人間」 だの不謹慎に唾を吐きまくる愉快痛快ブラックジョークの雨霰。こんなんでもメジャーから出てるんだからブームって凄いよなーとつくづく思う次第。
17. CASCADE 「80*60=98 FORWARD TO THE PAST」
CASCADE を
ニューウェーブ原理主義の知能犯と捉えるか、ブームに乗ってスターダムに飛び出したアイドルバンドと捉えるかは各人の勝手ですけども、そのアイドル臭さも確信的なものだとしたらもう何を信じていいか分かりませんね。
ニューウェーブ独特の
レトロフューチャーな艶やかさと脱力感をメインに据えつつ、古き良きパンク/ロックンロールのエッセンスもほんのり交え、斜に構えたユーモラスなアイディアと何気にキャッチーなポップセンス、実験性やルーツに対する憧憬も包み隠さず自由自在に繰り広げる。キュートなメロディが一際冴え渡った代表曲 「S.O.S ロマンティック」 「咲き乱れよ 乙女たち」 なども良いけど、フェミニンなイメージを覆す毒っぽさの 「la narracion grande」 からB級
テクノポップ全開の 「シグナルシグナル」 と、こちらの予想をガシガシ裏切るオープナーが痛快すぎる。 「80年代×60年代=現代」 というタイトルがあまりにも的確な、このバンドならではの
キッチュな味を存分に楽しめる一枚です。
16. Merrygoround 「REDDISH COLLECTORS NO DEAD ARTIST」
ダーク系ヴィジュの聖地である名古屋。そこの出身バンドの中でも一際強烈な個性を放っていたバンドです。独自の言語センスによるコミカルB級サイコホラーな世界観を追求しつつ、テクニカルな
変拍子を多用した楽曲は切れ味の鋭さと徐々に身体を侵食する毒素を併せ持ち、ひどくマニアックな異形の個性を発揮していました。それでこの作品は2人編成になってからの初フルレンス。瞬殺ハードコアチューン 「心臓」 「REDDISH MY CHAINSAW」 を筆頭により
ラウドロック色を強めながらも、それが単純にライブ向けのフィジカルな躍動感には繋がらず、何処かしら実験的で突き放したような冷たさばかりが残る、そんな変則的アグレッションがひどくスリリングで刺激的。終わりの見えない悪夢のような長尺スロウ曲 「ザクロ色の月と狂った恋の旋律」 「PSYCHO」 、彼らなりに余所行きのポップネスを目指したシークレット曲 「赤い絲」 もまた素敵です。現在ヴォーカルは当時のサポートと新バンド Smells を結成し、そちらの方も相変わらずの異形っぷり。
15. D≒SIRE 「終末の情景」
現在は
Kαin として活動する藤田幸也社長のバンド。頻発するメンバーチェンジのためまともに新曲が出来ず、アルバム4枚のうち7〜8割が同じ曲の録り直しというわけのわからん事態になってるのでどれ聴いても同じかもしれませんが、この初フルレンスは演奏や音作りがまだ整理整頓されてないぶんインディーズならではの濃さは随一。一言で言えば
クリーントーン主体のビートロックですが、音は正直言ってこっちが不安になるくらいペラペラ、だけども耽美的
ナルシシズム極まれりな歌詞と翳りのある切なさに彩られたメロディは抜群のコンビネーションで迫り、妙に説得力を持って聴き手を引きずり込む。
ラルクの透明感と
黒夢のスピード感、それらが 「切なさ」 を際立たせるという唯一の目的の下に配合され、ヴィジュアル J-POP としてある種のK点越えを達成した作品です。特に 「JESUS?」 「KISSxxx」 の怒涛の畳みかけには有無を言わさず圧倒されるし、シークレットのインダストリアル攻撃曲 「人口楽園」 も痺れるくらい格好良い。夢見る乙女は必聴。
14. GUNIW TOOLS 「FICKLE BOON」
持ち曲ほぼ全てにメンバー監督の PV が作られてたり、ライブでは
暗黒舞踏ダンサーや巨大気球を投入したりとニッチな異彩を放っていたバンド。視覚面に強い拘りを持ってるという意味では正しい意味での 「
ヴィジュアル系」 と言えるかもしれませんが、耽美と言うより西洋童話的な世界観とシニカルな歌詞は他にはないものだし、音楽的にはかなり洋楽志向が強く一般的なヴィジュのイメージと比べるとやはり異色。個人的には仄かに異国情緒漂う箱庭的ヒネクレポップスといった作風の3人編成時よりも、ラフな厚みのギターロックとエレクトロニクスが空間的に交錯する2人編成時の方が好き。それでこの作品は後者の編成によるラスト作。 牧歌的なメロディが大きなスケールで開ける 「MISTY GATE」 や、シューゲ風の甘美な陶酔を湛えたロックンロール 「Looser Sugar」 など細部まで十分に練り込まれた秀曲揃い。ロンドンレコーディングが功を奏した深みのある音作りも素晴らしいし、幅広い音楽的嗜好を自由奔放なアイディアで打ち出した素敵な一枚です。
13. La’cryma Christi 「Sculpture of Time」
当時
SHAZNA 、
FANATIC◇CRISIS 、
MALICE MIZER と共にヴィジュアル四天王として名を馳せたのも今や懐かしい話ですが、その中でも真っ当な実力派として個性を発揮していた彼ら。一般的にはヴォーカル TAKA の激甘ハイトーンや王子様ルックスばかりが取り上げられがちですが、そもそも出発点が
プログレ/ハードロックなだけに演奏力の方は申し分なし。複雑に絡み合いながら時にはミステリアスな浮遊感を見せ、時には重厚な迫力を持って迫るアンサンブルがバンドの持つ大きなポテンシャルをアピールしつつ、所謂
HR/HM 様式美やマッチョな肉体性とは少し距離を置き、中東エキゾチックな妖艶さを振り撒きながら大きなスケールで開けるメロディを中心に据え、あくまで J-POP として気持ち良く聴かせる。そんな彼らならではの手腕が全編で炸裂してます。特にポップスとして秀逸な 「Ivory trees」 「THE SCENT」 、幻想のような美しさを誇る 「偏西風」 など、ちゃんと対峙して聴いてみるとその聴き応え十分な
サウンドにただ唸らされるばかり。
12. zilch 「3 2 1」
当時 hide が Ray McVeigh や Paul
Raven とともに海外進出の足掛かりとして結成したプロジェクト。内容は彼の
ヘヴィメタル/インダストリアル成分を抽出、特化させた超攻撃型
サウンドです。この頃からシャープ & グルーヴィなモダンヘヴィネスを全編に導入しつつ、フリーキーなプログラミング音やサーフな軽快さのパンク/ロックンロール成分もそこかしこに散見、またその中に hide らしいユーモラスなアイディアやキャッチーさはしっかり健在。どの曲もフックの効いた抜群の即効性を持ってガツガツ身体に響いてきます。さらに歌詞は電気胡瓜だの湿ったヘビだの下世話なエロネタ大連発 (生々しい喘ぎ声もたくさん聴けるよ!) 。海外ラウド勢に勝るとも劣らないアグレッションと hide 本来の強烈な個性が合致した充実の内容であります。 「DOUBT」 「POSE」 など hide ソロ作のカヴァーも幾つかありますが、正直いずれもこの
zilch 版の方がアグレッションが際立ってて格好良いと思う。今聴いても余裕で刺激的。
11. V.A. 「GRAND CROSS 1999」
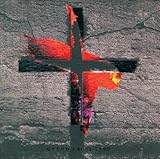
GRAND CROSS 1999
- アーティスト: オムニバス,JBK,d-kiku,SUGIZO,Les yeux,SATSUKI,ANGIE,REDRUM,bice,土屋昌巳,ケビン・ダビィ
- 出版社/メーカー: ポリドール
- 発売日: 1999/08/11
- メディア: CD
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
主催レーベル 「CROSS」 のコンピレーション盤。内容は彼のオリジナル曲のリミックス/リメイクに加え、国内外問わずリスペクトする先輩アーティストや新進気鋭の若手など様々、またそれらの音楽性もテクノ/
エレクトロニカ/ジャズ/
ドラムンベース/ヒップホップなど多岐に渡り、彼の持つ幅広いアンテナがそのまま反映された興味深い内容になってます。しかもその全てにおいて奥行きのある音像、高潔なポップ感は共通しており、ひどくヴァラエティに富んだ内容なのに楽曲の粒が上手く揃えられ、一つの主義主張に貫かれたトータリティを感じさせるという。コンピレーションとしてこれほど完成度の高い作品もそうそうないです。不穏かつクールなスリルが徐々に枝葉を伸ばすように広がる 「EXPERIENCE-1999」 、あまりの幻想的な美しさに陶然とする 「LOVE BIRD」 、ちっちゃくて可愛い
渋谷系ネオアコ 「The Girl In The Letters」 など。彼のアーティスト、またプロデューサーとしての手腕が遺憾なく発揮された逸品。
10. SCARE CROW 「立春」

知る人ぞ知る裏名盤。様々な音色を駆使するギターや複雑な変拍子/テンポチェンジをしなやかにこなすリズム隊、それらが静と動を行き来しながらセッション風の複雑な展開を見せるバンドアンサンブル。そこにピアノ/シンセ類や穏やかな波の音、人々のざわめき、静寂を切り裂くベルの音、そういった環境音が同化して一つの音世界を構築する。まるで小さな芽が徐々に枝葉を伸ばし、奇麗な花を咲かせて次第に枯れていく、その一連の様子を音だけで表現しきったかのような楽曲群。 「ニダイ」 「籠」 など荒々しさを見せる曲でも背後には静かな無常感が潜み、ピンと張りつめた緊張感も全てが午睡の夢だったみたいに何気なく過ぎ去っていく。プログレの構築美を純日本的モチーフや線の細く耽美な透明感と絡ませ、 「美しい情景がある」 ということをドラマチックな誇張抜きに、けれども雄弁に伝える。7曲22分という短い尺の中に徹底的な美意識が貫かれた、ひっそりと豊かな輝きを放つ傑作です。
9. L’Arc-en-Ciel 「True」
当時
ヴィジュアル系と言えば EXTASY 勢を筆頭にドギつい激しさ/荒々しさを際立たせるスタイルが主流だった所に、幻想的かつ妖艶な美しさを重視したクリーンな作風で異彩を放ち、結果多くのフォロワーを生んだ彼ら。この作品はその幻想性からさらに一歩外へ踏み出して国民的
ポップロックバンドへの道を歩み出した、その転機とも言える意欲作です。楽曲毎に違ったプロデューサーを起用して、 「Caress of Venus」 の流麗なハウス、 「the Fourth Avenue Cafe」 のホーンセクション、 「I Wish」 のクリスマス
聖歌隊など様々な趣向を凝らしてますが、それらのアイディアにまるでスベりハズしが見当たらず、カラフルな魅力として有効に機能してる。さらに中心のメロディは
ラルクらしい耽美な味を保ちつつ、よりキャッチーに突き抜けていて聴けばすぐ頭に残る。創作意欲に脂が乗っていた当時の勢いをひしひしと感じさせる、ミリオン突破も思わず納得するほどの充実した内容です。 「flower」 とか未だにカラオケでよく歌いますしね (笑) 。
8. SUGIZO 「TRUTH?」
LUNA SEA 活動休止中に行った各メンバーのソロ活動の中でも、やはりこの人の作品は頭一つ飛び抜けてた。15曲中本人のヴォーカル曲は7曲、ゲストの女性ヴォーカル曲が2曲、インストが6曲。当時彼が傾倒していた
ドラムンベース/ヒップホップなどのクラブ
サウンドと、バンド本隊で見せていた元来の持ち味を高次元で融合させた内容。本人の歌はやはり甘さが残るものの、ラウドもクリーンもリ
バーブもアコースティックも自分の色に染めるギタリストとしての強烈な個性が存分に発揮されており、その細部にまで至る構築性、完成度の高さに唸らされるばかりです。それぞれの曲が明確な個性/役割を持ち、在るべき場所に在るべき曲が存在する
組曲的構成で、 「EUROPA」 のミステリアスな浮遊感や 「Le Fou」 の息を飲む美しさ、 「CHEMICAL」 の狂気に 「SPERMA」 の不穏、そして 「LUNA」 の暖かな安らぎ、それらが 「真実とは?」 というコンセプトの下に連結、収束して一つの深遠な内面世界を築き上げてる。当時の彼のポテンシャルを振り絞った渾身の一発。
7. 黒夢 「CORKSCREW」
黒夢は時期によって方向性がまるで違うんで一枚を選ぶのが難しいんですけど、やはり思い入れで選ぶなら最初に聴いたコレ。2〜3分台のタイト & ファストな攻撃チューンが大半を占め、以前の甘さ切なさはほとんど無し。性急なビートに超キャッチーなサビが乗った 「FASTER BEAT」 「CANDY」 「ROCK'N'ROLL」 は
メロコア、 「HELLO, CP ISOLATION」 はスカ、 「YA-YA-YA!」 ではレゲエも取り入れたりとほぼ完全に
ラウドロック化。90年代後半は
ヴィジュアル系と
HI-STANDARD や
KEMURI などに代表されるパンク/
メロコア系、2つの大きなブームがありましたが、このアルバムはその2つの類稀な
クロッシングポイントと言えるんじゃないかと。海外レコーディングが功を奏したのかソリッドで迫力ある音作りになってるし、今でも古臭さなどを感じず十分聴ける強度を保ってる。シリアスな歌モノのシングル曲 「少年」 「MARIA」 は若干浮いてる気もしますけど、それを差し引いても十分お釣りのくる痛快作。
6. hide 「PSYENCE」
「おもちゃ箱をひっくり返したような」 という
クリシェはこのアルバムのためにあるようなものです。前作 「HIDE YOUR FACE」 よりもさらに音楽的自由度が高まり、彼のエンターテイナーとしての才能が遺憾なく発揮された内容。スパイ映画風ビッグバンド×ヒップホップ SE に始まり、軽快に躍動するギターロックはもちろん、獰猛に牙を剥くインダストリアル/メタル、薄汚くささくれ立った
グランジ/
オルタナティブ、カラフルさに輪を掛けるテクノ/音響、そういった節操無いほど多岐に渡る音楽ジャンルが hide ならではの軽妙なポップセンスで纏め上げられ、同一線上にズラリと陳列されてる。縦にも横にも大きな広がりを見せる、言わば音楽の総合
アミューズメントパークであります。でも 「限界破裂」 とか、能天気にふざけてるフリして歌詞は意外に辛辣だったりするから侮れない。ヘヴィとポップ、王道と実験、ユーモアと真摯、そういった相反する要素が何重にも張り巡らされた、刺激的な仕掛けだらけの突然変異ポップ作。
5. 筋肉少女帯 「月光蟲」
キャリアが長いだけにそれぞれのアルバムが違ったコンセプトを持ち、その中には名曲も多いけど迷曲も多い
筋少ですが (笑) 、個人的に一枚選ぶとしたらこの作品ですね。メジャーの聴きやすさとアングラの毒素、双方のバランスが高いレベルで両立されてるのと、楽曲の粒が上手く揃ってて全体の流れが良く、
筋少のカタログ中最もトータリティが優れてると思う。 「猫のテブクロ」 以来の新体制での方向性を突き詰め、楽曲のクオリティの向上に加えてアンサンブルはさらに強靭なものとなり、
オーケンの歌詞は猟奇的かつ文学的な深みを増してる。力強いストリングスを導入したポップサイドの傑作 「サボテンとバントライン」 や高速
ポルカメタル 「イワンのばか」 、やたら陽気でファンキーなノリが逆に毒々しさを浮き彫りにしてる 「僕の宗教へようこそ」 など秀曲/代表曲揃いの充実した内容。初心者の方は是非ここから迷い込んで帰って来れなくなって下さい。しかし改めて思うけどやっぱりこんなバンド他には絶対ない。
4. MALICE MIZER 「merveilles」
宝塚劇団かと思うくらい (俺は当時本当にそう思った) 豪華絢爛な中世ヨーロッパ風衣装、幻想的ロマンチシズムに満ち溢れた歌詞世界、時には楽器を弾かず踊りに徹する演劇的ステージングと、ロックバンドの枠に囚われず 「
ヴィジュアル系」 という表現形態の極北を開拓したパ
イオニア的存在の一つ。その音楽的/視覚的な世界観の構築っぷりはとにかく
インパクト絶大で、特に
Gackt 在籍時のこの作品は神懸り的にコンセプトが完成してた。見た目通りに重厚なクラシカル要素ももちろん導入しつつ、
ネオアコ風の軽やかな 「Brise」 や
ユーロビート調の 「Ju te veux」 、タンゴ要素を取り入れた 「
月下の夜想曲」 など様々な音楽性にトライしており、それら全てをキャッチーな感傷に満ちたメロディでキッチリ纏め上げ、聴き応えのある濃さでもって強く胸を打つ。
Gackt の表現力豊かなヴォーカルも非の打ちどころがないし、純粋にポップアルバムとして一級品。決して単なるこけおどしには終わらない、説得力が十分に備わった一大ファンタジアポップ傑作です。
3. BUCK-TICK 「Six/Nine」
ヴィジュアル系オリジネイターの一つであり J-POP 界の異端者。 「狂った太陽」 以降現在に至るまでコンスタントに傑作を連発、物議を醸す問題作はあっても駄作は一切作らない怪物バンド。そんな御大のキャリア中最も毒素の強い作品がコレです。従来の妖しいメロディセンスやノイズ/インダストリアル由来のプログラミング音に加え、この頃は比較的
HR/HM 要素が強く 「love letter」 や 「唄」 なんかは正しく B-T 流ヘヴィロックといった作風ですが、当然それだけの単純な物では収まらない。タイトルが示す輪廻というコンセプトの下に 「君のヴァニラ」 ではディープな性欲、 「鼓動」 では生に対する深い感謝と希望、 「限りなく鼠」 や 「デタラメ野郎」 では存在理由への倒錯的な問い掛け、そういった生/死/セックスに関するタームが全16曲、70分超の大ボリュームに渡ってグルグルドロドロ渦を巻く。その圧倒的な密度の濃さ、世界観の構築性は他を寄せ付けないほどに突き抜けてます。 彼らの目指す方向性がここで一つのピークを見せた、超重量級の名盤。
2. LUNA SEA 「MOTHER」
今の若手ヴィジュの一番直接的な影響元であろう月海。でもその凡百の若手が束になっても敵わないのは彼らが単なるビートロック歌謡バンドではなく (もちろん単純にメロディが良いのでそういう聴き方もできますが) 、キメ細やかな疾走感を流麗にこなす鉄壁のリズム隊や複雑に練り込まれた重層的ギター
サウンド、それらが緻密に重なり合って透明感とダークネスを併せ持った深遠な奥行きを生み出す、そんな個性豊かなプレイヤーが織りなすバンドアンサンブルの完成度の高さがあるからです。ヴィジュアルショッカー国家 「ROSIER」 「TRUE BLUE」 はもちろん、徐々に神秘的なスケールを広げていくオープナー 「
LOVELESS」 、重心を低く構えたヘヴィグルーヴが格好良い 「FACE TO FACE」 、パンキッシュな荒々しさで捲し立てる 「IN FUTURE」 、そして深い憂い/悲しみが壮大に木霊する表題曲
「MOTHER」 と、頭からケツに至るまで彼らの確固たるポリシーが貫かれた、代表作にして金字塔。ちなみに俺の叔母さんも大ファンです。
1. Plastic Tree 「Puppet Show」
彼らが影響を受けたと公言する
The Cure 、 Bauhaus などのゴシック/
ポジパンに通じる美意識と、
Nirvana に代表される
グランジ/
オルタナティブの暴力性の奇跡的な融合。以前よりも音の厚みやグルーヴ感が格段に増したのに加え、ヴォーカルは中性的な浮遊感に加えてヒステリックな絶叫も飛び出すようになり、それらが時には叙景的に、時には痛々しく心情を吐露する歌詞と相まって、深く心に突き刺さってくる。 「May Day」 や 「リセット」 、また前ヴァージョンよりもグッと迫力の増した 「本当の嘘」 「クリーム」 は単純にロック曲として凄く格好良いし、オーケストラを従えて深遠な広がりを見せる 「幻燈機械」 、静と動の極端な対比で感情のメーターが振り切れた 「『ぬけがら』」 「3月5日。」 、ディープな奥行きと切ないメロディが響き渡る大曲 「サーカス」 と、表現の幅が一気に増してスロウな長尺曲でも緊張感が緩まず強い求心力を放ってる。歪んだポップ感を打ち出したブックレットも凄くセンスが良いし、もう何回聴いたか分からない、俺にとってひどく業の深い一枚です。
こんな感じで、世間一般で名盤と謳われてるものに多少色目を使いつつ (笑) 、基本的に自分の個人的な思い入れを重視しました。自分以外の誰かが言う名盤なんて結局そんなもんですし。あと 「今でも聴ける」 というのもポイントの一つ。90年代初頭の音源なんかは特に、曲が良くても音質がショボすぎて聴いてられないというのが沢山あるので。しかしこうして見ると基本的にどの作品もポップなのだけど、へヴィだったりアングラだったり陶酔度が高かったり、何かしら捻れた濃さを持ってて取っつきやすさとともに引っ掛かりの強さも備わってると言うか。音楽性バラバラなようで共通点がある気もするし、自分の嗜好が再確認できたようで面白かったにゃー。とりあえず上で挙げたものの半数以上はブックオフとかで簡単にサルベージできるはずなんで、暇があれば聴いてみると良いと思いますよ。以上回顧厨が送る1990年代ヴィジュアル系名盤20選でした。